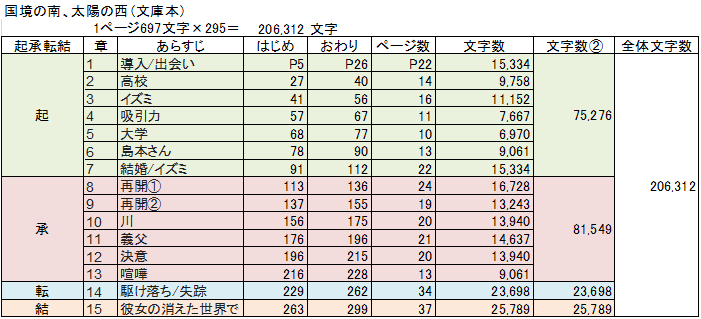2010年3月「志帆の話②」
二度目の大学受験を終えた志帆をスノーボードへ連れて行ってやった。夏休み以来頻繁に志帆から連絡が来るようになって、受験が終わったらゲレンデに連れて行って欲しいとねだられていたのだ。
志帆は残念ながら第一志望の大学へ行くことは叶わなかった。彼女が必死で勉強している間、何も考えずに悠々自適な学生生活を送っていたことに少なからず申し訳なさを感じていた僕は、できる限り彼女の労をねぎらってやりたいと思っていた。
僕たちはこの半年のメールのやりとりだけで随分仲良くなっていた。基本的には彼女の方から一方的に質問をしてきて、僕がそれに答え質問を投げ返すというやり取りが多かった。彼女が僕のことを「アユム」や「お前」と呼びつけにすることもあって、僕は彼女に必要以上の気を遣うこともなかった。志帆がローリーと仲が良かった理由や、男友達が多い理由もわかる気がした。
三月十四日、ホワイトデー。約束の時間を少し過ぎて待ち合わせの場所に到着した。志帆はしばらくやって来そうになかったので、僕は三月の心地よい陽だまりの中でタバコに火をつけた。
空は綺麗に晴れていて雲ひとつなかった。どこかから日本人形店の宣伝放送が聞こえた。いったいどんな人がこの宣伝に耳を傾け、どんな人がこの宣伝を頼りに日本人形を買い求めに行くのか、僕には皆目見当もつかなかった。
志帆はそれから五分ほどしてやってきた。彼女に会うのは夏以来だ。志帆にiPodを渡すと、彼女は一曲目にエアロスミスの「イート・ザ・リッチ」をかけた。ハードロックを聴きながら高速を運転するには最高の天気だった。
スキー場は若い客で賑わっていた。僕たちはボードと靴をレンタルして更衣室でウエアに着替え、早速リフトでゲレンデを登った。コースの雪はこの天気でかなり解けてしまったらしく、何箇所かは土が露出していた。
ゲレンデの上からは晴れ渡った冬の青空に包まれる街を一望することができた。下から見るとそれほど高そうに見えないコースも、上から見下ろすと思ったよりも傾斜があり足がすくんだ。
志帆はもう何度もスノボーをしたことがあり、僕にスノボーを教えてくれるという話だった。スノボー経験二回目のビギナーである僕は志帆に先に滑るように促した。
「先に滑ってみてよ」志帆がそう言うので、仕方なく僕は腰を上げた。
恐怖で思ったように身体が動かない。最初何度か雪の軌跡にボードをとられ勢い良く転んだが、僕は少しずつ感覚を取り戻し、ボードの楽しみ方を思い出た。
志帆の様子を確認しようとゲレンデを振り返ったが、彼女はまだ頂上で座っている。僕はまたしばらく滑ってからコースの中腹で座って待っていたが、志帆がなかなか降りてこない。不思議に思った僕は志帆に手を振って下りてくるように促した。
すると彼女は恐る恐るバランスを取りながら腰を上げ、ゆっくりと重心を前へ移した。そしてそのまま一度も方向を変えることなく猛スピードでコースの脇にあるネットへ突っ込んで行った。そんな志帆の姿を呆然と見ていたが、あまりの間抜けな姿に僕は笑いが止まらなくなってしまった。僕はボードを外し、歩いて志帆のいるところまで登り、ネット際でもがいている彼女を助けてやった。
「ボードやったことあるんだよね?」
「小学生以来だから、滑り方忘れちゃったのかも。悪いけど教えてくれる?」と志帆はばつが悪そうに言った。
なぜスノボー二回目のビギナーが経験者に滑り方を一から教えなきゃいけないんだ? と思いながら、さすがにここまできて滑ることができずに帰るのは気の毒だと思った僕は、志帆に滑り方を教えてやることにした。
先に僕が少し滑って、志帆がうしろを転がりながらついてくる。それを何度も何度も繰り返して、下まで下がったらまた上まで上がる。初めのうちはリフトに乗りながら彼女の両親の話や、アパート選びで起こった母親とのいざこざをいろいろと聞きいていたが、しばらく繰り返すと次第に話すこともなくなった。
日が沈み、ゲレンデの人の数も減ってきた。五時になるとゲレンデにアナウンスが流れ、昼の営業時間が終わった。大きなキャタピラの雪上車が雪を均すためにゲレンデを登っていった。本当はもう帰ってもよかったが、志帆がナイターもやりたいと言うので、僕たちは食事を済ませてからナイター用のリフト券を買った。喫煙所でタバコを吸って戻ってくると、スキー場の従業員がゲレンデにキャンドルの飾りつけをしていた。志帆はデッキの手すりにもたれかかり、僕に何か聴いてほしそうな顔でキャンドルを見ていた。
僕たちは何も言わずにスノボーを再開した。辺りはもうすっかり暗くなり、夜の冷たい風が顔を刺すようになった。
ゲレンデのアナウンスが花火の時間を知らせる。八時から花火が打ち上げられるみたいだ。志帆はこれを見たかったらしい。僕たちはゲレンデを登って、頂上から寝そべって花火を見た。
特に話すこともなかったし、何かを話すような空気でもなかった。小さく質素な打ち上げ花火が、冬の夜空に咲いては散っていった。空も澄み渡って星が綺麗だった。眼下の街の小さな明かりが一日の終わりを告げていた。とてもロマンチックだ。僕の隣ではスキーウェアを着た十九歳の女の子が座って夜空を見上げている。周りの客はカップルしかいない。いったいこのシチュエーションはなんなんだ?
「花火綺麗だったね」僕たちはそう言ってゲレンデを下までゆっくり降り、着替えて温泉へ向かった。
よほど疲れたのか、温泉から上がった志帆はほとんど口もきかずに、帰りの車の中で眠ってしまった。僕はコンビニで缶コーヒーとタバコを買い、睡魔を追い払うためにアイアン・メイデンを一人で口ずさみながら田舎の夜道に車を走らせた。志帆を家に送り届けて、そうして一日は終わった。
☆
数日後、大学の長い春休みに暇を持て余していた僕は、一人で越後湯沢に行くことにした。「雪国」のトンネルが見たくなったからだ。タイミングよく志帆から連絡があって、どこかに連れて行ってくれというので、彼女を誘ってみることにした。
「私この前のボード結構楽しかったな、って次の日の朝起きて思った」
「それは良かった。自分から行きたいと誘っておいたくせに全然滑れなくて、おまけにつまらなかったと言われたら二度と誘わないところだったよ」
僕たちは朝九時に高速に乗って新潟を目指した。到着予定は五時だ。志帆のiPodでエアロスミスを聞きながら高速をひた走った。ナビに従い高速を降りどこかの川沿いを走っているときに、なぜか車内の空気が変わった。どんな話の流れでそうなったのかわからないが、志帆は急に怒りだした。
僕が彼女を誘った理由が気に入らなかったみたいだ。僕は志帆がどこかへ連れて行ってくれというから、彼女を誘ってやったのだ。その「誘ってやった」という言い方にどうやら問題があったみたいだ。
「じゃあお前はなんで付いて来たんだよ。別に温泉に行きたかったわけでもないだろ? ただ家に居たくなかっただけでどこかに連れてってくれる相手なら誰でも良かったんだろ?」僕がそう言うと志帆は黙った。
「俺も悪いしお前も悪い、これでチャラだろ。はあ」
「今のは何の『はあ』?」志帆が突っかかるように言った。
「こんなに遠くまで良くわからない人を連れて来ちゃったな、の『はあ』だよ」僕がそう言うと志帆はまた怒り出した。
「なんかスッキリしない」
「じゃあ何がスッキリしないんだよ」
「もういい」志帆はふてくされて助手席側の窓を睨みながら言った。
「俺がよくないんだよ。お前がスッキリしないと俺もスッキリしないんだよ。お互いスッキリするために今なんでお前がスッキリしてないのかを二人で考えよう」
「なんかそういうのがむかつくんだよお前!」
こんな調子で新潟に入った。
そのまましばらく出口の見えない会話を暇つぶしのつもりで続けていると、知らないうちに僕たちは和解していた。こういう討論があったほうが人との仲は深まるのだ、きっと。
それからの会話は楽しかった。志帆の生い立ちや、中学高校の思い出、彼女の両親の話をしながら雨の峠を越え、湯沢に入った。道の脇にはものすごい量の雪が積もっていて、その光景はまさに「雪国」そのものだった。
小雪のぱらつく土樽駅はとてもひっそりとしていて誰一人居なかった。駅前の道は下りの階段になっていたが、雪で埋め尽くされ降りることができなかった。少しだけ顔を出した階段の最上段に腰を下ろし、眼前に迫る雪山を眺めながらタバコを吸った。きっと川端康成もこの景色を見ていたことだろう。しかし、それがいったいなんだっていうんだ?
僕たちは清水トンネルへ向かった。トンネルは新旧の二本あった。深く積もった雪の上を通り線路まで出て、二人でトンネルを眺めた。これが世界で一番有名な日本の「トンネル」だ。異世界への入り口のような大きな穴が、深い雪の中にぽっかりと空いていた。その100パーセントの暗闇は僕たちを手招きしているように見えた。今ここに飛び込んでも僕には失うものなんて何もないように思えた。
その後僕たちは温泉向かった。内湯が一つしかない質素な風呂だった。温泉を上がった頃には時刻はもう六時を過ぎていた。先に上がった僕は車へ戻って今日の宿を探してみたが、安い宿はどこも満室だった。あきらめてタバコを吸い、番台の前の椅子に座って志帆が出てくるのを待った。
雪できれいに染まった山と空を低く覆い隠す雲がスキー場のオレンジ色の明かりを反射し、夜になっても町全体が奇妙に明るかった。
帰りの車の中、僕たちはお互いに家族のことや昔の友人のこと、これから始まる新学期について仲良く話しをした。行きに通った峠道をひたすら戻ったが、対向車は一台も通らなかった。気が付くとさっきまでどんよりしていた空からは雲が消え、綺麗な星が見えた。
僕は自分でも知らないうちに、この訳のわからない女に少しずつ心を開きはじめていた。車内には二人の会話とドン・ヘンリーの暖かい歌声が響いた。
高速に乗り、サービスエリアで食事をとることにした。僕は食事を済ませてから一人でタバコを吸った。そこからは千曲市の街を一望することができた。長野の澄んだ空気に包まれた街の明かりが美しく輝いていた。志帆を誘って一緒に見ようかと思ったが、訳のわからない空気になるのが面倒でやめた。
古いジャズを聴きながら運転を続けた。途中エンプティーランプの点灯に気づき急いで高速を降りたが、田舎の国道沿いのガソリンスタンドはほとんど閉まっていた。やっと見つけたセルフのガソリンスタンドで給油し、そのまま志帆を家に送っていこうと思った時、「ねぇ」と志帆が言った。
「やっぱりいいや」
「なんだよ、気持ち悪いな」
「いや、もう帰っちゃうのかなーって」
「じゃあ、どこか寄って行こうか」
どこかで聞いたことのある台詞だ。
確かにこのまま帰ってしまうのは少し寂しい気がした。お互いに心の距離が縮まったということなのだろうか。明かりの少ない川沿いの道を見つけて、堤防の上に車を停めて星を見ることにした。地元の星は綺麗だ。
全く星座の名前を知らない志帆に、あれが何座でこれが何座ですと言って説明してやった。オリオン座を知らない十九歳がいていいものか? 三月の寒空の下、僕たちは車に乗せてあった薄いタオルケットに包まって二人で星を見続けた。
いわゆる美しい容姿を持つ女の子と一緒に、こういった非日常的で幻想的な空気に包まれると、どうしても自分が男で隣に居るのは女の子なんだということを考えてしまう。そして僕たちが異性であることを思い出した途端に、そこに大きな壁のようなものが生まれ、やり場の無い虚しさや歯がゆさを感じる。おまけにその女の子は中学生時代のアイドルで、ついでに僕のストーカーだったなんて聞かされて、そんな空気の中で正常な理性を保てるのか? と僕は思った。
しかし一方で、「そんな不確かな感情ではもう俺の心を動かすことはできない。結局こんなものは俺の求めているものを何も訴えかけてはこないのだ」と懸命にあらがう妙に子供じみた理性がいた。理性を性的欲望の奴隷とするには僕はまだ青すぎるみたいだ。なんだか僕はつまらない人間になってしまったなと思った。僕は望んでそうなったのだろうか?
そんなことを考えている間に、流れ星がいくつか視界を通り過ぎた。お互い寒さに耐えかね暖房の効いた車の中で横になった。東の空が明るくなり始め、冬の冷たい夜空が少しずつ溶けていった。お互い一睡もしないまま朝がやって来た。車内ではシンディ・ローパーの「タイム・アフター・タイム」が流れていた。
志帆の家の近くの公園に車を停め、ベンチに座って日向ぼっこをした。行きに買った赤のポール・モールも最後の一本になっていた。志帆と他愛も無い会話をして、彼女は家に帰っていった。すがすがしい朝だった。朝露にぬれた芝や遊具や古い民家が春先の朝日に照らされ眩しく輝いていた。
無事家にたどり着いた僕は飼い犬の熱烈な歓迎を受け、タイム・アフター・タイムを聞きながら熱い風呂に入り、訪れたばかりの春の香りの中で暖かい眠りについた。
☆
それから数日後、僕は母親の車をジャックし、ローリーとタックと三人で二週間ほど西日本を旅した。ここであえて「旅」と表現するのは、それが旅行と呼ぶにはあまりに粗末な代物だったからだ。
僕たちは最初の二日間を使って能登半島最北端を目指したあと、週末のレースのため阪神競馬場に向けて南下した。阪神大賞典で大敗を喫した我々はその日のうちに広島に入り、翌日広島城を観光した。広島のファミレスでローリーが「縄文杉が見たい」と言い出し、鹿児島港へと南下した。ここまですべて車中泊だ。
屋久島に到着した我々はウェアやシューズといった登山ギアをレンタルし、翌朝早く縄文杉を目指して山を登った。手付かずの自然に囲まれ、マイナスイオンたっぷりの霧を肺いっぱいに吸い込み、文明社会の時間の流れの慌ただしさを思った。今にもサンやこだまが姿を現しそうだった。
何度か激しい雨に打たれ、そのたびに我々は大きな木の下や岩陰で雨宿りをした。太鼓岩に到着した時には雨は止み霧も晴れ、岩の上からは屋久島の大自然を一望できた。ちらほらと見える白い桜が春の到来を告げていた。
太鼓岩を過ぎ弁当を食べ、一度下って縄文杉を目指す。ところが縄文杉への分岐路へ到着したころには時刻はすでに十六時を回っていた。他の登山客は皆下山を始めている。ガイドとすれ違うたびに「こんな時間に上るのか!?」と驚かれ、「霧が濃くなったらすぐに下山を始めるように」と何度も念を押された。ここまで来て引き下がるわけにはいかない。我々は走って縄文杉を目指すことにした。
岩をよじ登り、木の根を飛び越え、ぬかるんだ斜面を蹴り、我々はひた走った。三十分ほど走ったころにすれ違ったガイドに「私たちで最後の下山者です」と言われ、それから先僕たちは三人だけで縄文杉を目指した。非日常性と緊張感からか、自然と疲労は感じなかった。縄文杉までの道中、いくつも巨大な杉の木を通り過ぎた。そのたびに僕は、これが目的の縄文杉か? と期待を込めて看板を覗き込んだが、どれも縄文杉ではなかった。それらの杉の木も充分すぎるほど立派であったため、僕の中の縄文杉への期待は高くなっていった。
ただ目の前の一歩に集中し、我々は三人で縄文杉まで走った。先頭を走る僕がその階段に差しかかった時、明らかに空気が変わった。ゆっくりと顔を上げると、そこには霧に包まれた、今までに見たこともないほど巨大な杉の木がそそり立っていた。もはや確認などする必要はなかった。それが縄文杉であることは一目でわかった。階段を登り切った僕は、縄文杉を前に立ちすくんだ。巨木の放つ神々しいオーラに包まれ、その息吹を吸い込んだ僕は、自分でも知らないうちに涙を流していた。とても神秘的な体験だった。
少し遅れてローリーとタックが到着した。僕たちは言葉もなく、ただ縄文杉を眺めた。「十五分経ったら山を下りよう」僕がそう言うと二人はただうなずいた。二人も幻想的な空間を楽しんでいるみたいだった。
僕は屋久島で何枚も写真を撮ったが、縄文杉の写真は撮らなかった。ここで写真を撮ったとしても、僕が覚えた感動はたぶん何一つとして伝わらないだろうと思ったからだ。縄文杉が見たくなったらまたここへ来よう、そう思って山を下りた。
ガイド達が言った通り、五時を過ぎると急に霧が濃くなってきた。僕たちは登ってきた道をひたすら走って戻った。もちろん誰ともすれ違うことはなかった。一番体力のないタックが遅れだした。気が付くとタックの姿は濃霧の中に完全に消えていた。
山を下りた頃、時刻は六時を回っていた。五分ほど待ったがタックは戻ってこず、探しに行くのはもはや不可能なほど霧が出ていた。五メートル先が完全にホワイトアウトしていて、あたりもどんどん暗くなってくる。「七時になってもタックが戻ってこなかったら救助を呼ぼう」そう言って僕たちはカッパを脱ぎ、タバコに火をつけた。
タックはそれから四十分ほどして降りてきた。ちょうど三本目のタバコに火をつけたところだった。僕たちはほっとして、「あと二十分おそかったら救助を呼ぶところだったよ」と言うと、タックは「マジで死ぬかと思った」と言って笑った。
翌日鹿児島港まで戻った僕たちは別府まで北上し温泉に入った。その翌日には四国でうどんを食べ、N市に帰った。その旅は十代の僕たちにとって本当に貴重な体験となった。
☆
長かった春休みも残りわずかとなった三月のおわり、僕は実家の荷物をS市のアパートへ運ぶついでに東京で志帆と飲むことになった。先に東京に帰っていた志帆と合流するため、僕は志帆のアパートの近くに車を停め、一人電車で新宿まで向かった。
待ち合わせ場所はJRの西口だった。志帆を待つ間喫煙所を探したが、そんなものはどこにもなかった。タバコを吸うことをあきらめた僕は新宿西口の慌ただしい人々の流れを見るともなく見ていた。駅にはスノーボードを担いだ学生の集団や、若いカップル、疲れ果てたサラリーマン、そんなくだらない連中であふれていた。
しばらくすると志帆がやってきて、僕たちは歩いて西新宿の居酒屋へ向かった。居酒屋に入るととりあえずビールで乾杯し、仕事終わりのサラリーマンが放つ雑音の中で枝豆をつまんだ。酔っ払った部下がわけのわからないことで泣き出し、酔っ払った上司がそれを見て本気でキレたりしていた。
僕たちは別に何を話すわけでもなくただただその場の空気に身を任せてグラスを空にした。飲んだわけでも食ったわけでも、楽しかったわけでもつまらなかったわけでもなかった。店を出る頃には客は僕たちだけになっていた。
終電で稲田堤まで戻り、志帆のアパートまで歩く。駅を降りたところで志帆のアパートが男子禁制であることを知らされ、僕は息を殺して彼女の部屋へ忍び込んだ。一週間前に引っ越しを済ませたばかりの志帆の部屋にはまだ女の子独特の匂いというものが無かったが、部屋そのものが志帆のパーソナリティを面白いほど表していた。ショッキングピンクのぬいぐるみ、山積みにされた参考書、70年代ロックのCD、無機質な東芝のノートPCとコードの絡まった黒いマウス、母親に持たされた健康食品の段ボール。志帆はコンビニに行ってくると言って一人で部屋を出て行った。
ベランダからの景色なんてものは無かった。ただ正面に別のアパートの壁が見えるだけだ。電気の消された他人の部屋の中で寝そべって天井を見上げる。僕は今なにをしているんだ?
しばらくすると志帆が帰ってきた。彼女は届いた小包から新しい腕時計を取り出し一人でニヤニヤしていた。受験が終わったら買おうと決めていたバーバリーの腕時計だそうだ。志帆は長すぎるベルトを解体する作業をしばらく試みたが、どうやら失敗に終わったみたいだ。
僕が先に風呂に入った。風呂から上がると、志帆は僕が持ってきた「羊をめぐる冒険」を読んでいた。志帆はベッドの隣に「宇宙服に使われてるナントカ」という素材で作られた銀色の薄いレジャーシートみたいなものを敷いて、僕の寝床を作ってくれた。彼女が風呂に入っている間、僕はその宇宙のナントカの上で寝そべって本を読んだ。鯨のペニスと耳の女だ。
志帆が風呂から上がると、僕たちは寝支度を済ませて消灯した。消灯した部屋には隣のアパートの階段の常夜灯が冷たく差し込んだ。
「明日の予定は?」と志帆は薄明りの中で天井に向かって話しかけた。
「S市のアパートに行って荷物を下ろして、M市で温泉にでも浸かって帰ろうと思ってたところだよ」と僕は応えた。
「M市の温泉、私も行きたいなあ」と志帆が言った。
「M市の温泉にお前を連れて行ったら、また東京まで送り届けなくちゃいけないだろ。そこからN市に帰ろうと思ったら一日じゃとても無理だよ」と僕は言った。
「じゃあ、今からS市に行って、明日の朝M市の温泉に向かうってゆうのはどう? そうすればアユムも明日中にN市まで帰れるし、何より明日明るくなってからこそこそとこの建物を抜け出す必要もなくなると思わない?」と志帆は行った。
「確かにそうだけど、M市から東京までの往復400キロは加算されたままなんだね」と言って僕は笑った。
結局志帆の提案を呑む形になって、僕たちは車でS市に向かった。二時間ほど高速を走って、僕のアパートに到着したのは午前五時だった。僕はサービスエリアで買ったパーラメントをくわえてベランダに出た。街はすでに朝を迎えようとしていた。左手には丘の傾斜を覆うように並ぶ住宅地、右手には送電線でつながれ整列した鉄塔たちとS市の街が見える。十一階建てのマンションと、新幹線の線路。遠くに見える山々。なぜか少し懐かしい風景のように思えた。僕がタバコを吸っている間、志帆も部屋の中でカーテンに包まってそんな景色を一緒に眺めていた。ベッドを勧めたがここでいいと言うので、僕がベッドで、志帆はこたつで眠った。
☆
翌朝、僕は志帆に起こされて目を覚ますと、時刻は十二時を回っていた。志帆はシャワーを浴びて、僕がその間に温泉を調べた。高速でM市へ向かう道中、志帆の幼少時代の話をした。どんな幼稚園で、どんな子がいて、どんな先生がいたとか。ガールスカウトに入って、どんなことを覚えて、どんな唄を歌ったかとか。三時間もあればいろいろなことが話せる。
M市についてからいくつか温泉を回った。最後にサウナのついた大きな風呂に寄って、そこで夕食をとった。約束の時間に風呂から上がったが、志帆がまだ出てきていないようだったので、先に外へ出てタバコを吸った。月が綺麗な夜だった。黒いマントを着た長髪の欧米人が風呂から出てきて、自転車に大きな荷物を積んでよろよろと帰っていった。志帆が出てきたと思ったら、彼女は電話をしていた。また母親ともめているみたいだ。志帆は終始呆れたような口調で母親を説き伏せようとしていて、母親は何度もそれに食い下がっている様子だった。おかげで僕はすっかり湯冷めしてしまった。
僕が二本目のタバコを根元まで吸い終わるころ、ようやく電話は切れた。僕たちは車に乗って東京へ向かった。行きと違って帰りの車内は静かだった。サービスエリアで休憩するために一言口を利くまで、お互いに一切口を開かなかった。僕はサービスエリアの喫煙所で深くタバコを吸った。見知らぬサービスエリアで吸うタバコは格別だ。再び車を走らせても、僕たちは黙っていた。デイビッド・ギルモアのギターが車内に悲しく響く中、僕は今の我々がすべき会話について考えていた。そんな風にしてただ一切は過ぎて行った。
高速道路を降りて志帆のアパートに向かう間、僕は彼女と一緒に過ごした数日で感じたことや考えたことを包み隠さず話した。この休みの間に二人の距離はずいぶん縮まったように思えた。
「たぶん、次に会うのは夏休みだろうな」と駅前に車を停めてから僕は言った。
「そうね。また温泉に連れて行ってね」と志帆はにこにこしながら言った。
「素敵なキャンパスライフを」と言って僕は志帆に手を振り、一人家路を急いだ。
おわり